
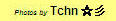
マヤの伝説
ママルーナ
(1)
?今から二万年前。洪積世のウイスコンシン氷河期 。 ユ −ラシア大陸に住む多くの部族は北東に移動し、ベーリ
ング陸橋を通って波状的にアメリカ大陸へと渡った。
新大陸での彼らは何千年もの歳月を費やし 南下をし続 け、小部族ごとに南北アメリカ大陸の各地に散在し定
住して行った。それら部族のうち、マヤ族はメソアメリカのコパンの地を中心に定着した。 ?
七番目の花の日。天蓋をを渡る太陽と月がその軌道を 完全に同一とする日の新月の深い夜、天文学者ヤシ
ュクックを父にその妻マルガリータを母に九番目の娘 としてママル−ナは生れた。 それは 太陽と月とが新
しく生まれ変わる日であった。夜が明け太陽が上らなければ 世界が 終焉するはずであった。
人々は恐れと希望との混沌のなか、丘の上につどった。 やがて、「見よ」 深い鮮紅色の金星を指差しながら
ヤシュクックが叫んだ。無数の黄金の矢が放射し始め天蓋に満ちた。
真昼の天体のドラマは更に展開し、正午、太陽は金の環
のなかに隠れ、やがて再び生れ変り、その新たな姿を現した。人々は溢れるばかりの厳かな新しい陽光のな かにひざまづいた。
(2)
揺りかごのなかの幼いころからママルーナはコンゴウインコと
共に育った。このインコはパコと名づけられていた。彼らはいつも一緒で、互いに付かず離れず空気同士のよう な
存在であった。彼らは聞こえない声の領域で話し た。彼らは互いの心と思いを共有していた。
マヤ族にとって太陽は森羅万象の父であり、大地は母で あり、そして地下は母の子宮であった。洞窟は神聖な
場であり、コンゴウインコは地下で暗闇と死と戦う太陽の象徴であった。
マルガリータはママルーナに読み書きを教えた。彼女は
やがて宮殿の中央にある広場に建立されている記念碑に刻まれている膨大量の記録を読破し、中でも彼女は
何千年もにわたって集積されている天体観察の記録の虜(とりこ)になって行った。
ヤシュクックは折につけ彼女を天文観測台へと伴い天文 学の基本を教えた。成長した彼女はヤシュクックと肩
をならべるほど天文学に精通するようになっていた。
北斗七星の周辺から降る異常なまでの夥しい数 の流れ星の耀きに天は満ちていた。ママルー
ナは目を南方んj転じた。はるか天蓋の南端の奥に目には見えないなにかが金色に耀いているように感じた。それが何であるかという不思議な思いから彼女は心のなかでなにごとかを呟いていた。
ある日彼女はヤシュクックに言った。天蓋には白金に輝くスポットと絶対的に黒いそれとの二つがある、と。そしてまた、天界は立体ではなく何次元もの世界で成り立っている、と。ヤシュクックは笑って相手にはしなかった。
(3)
アイマラ族の青年ナパクスコはチチカカの湖畔で煌く星 々の 下に立っていた。天は南十字星のあたりから降る夥しい数
の流れ星にあふれていた。はるか彼方、天蓋の北の末
端の奥から来るプラチナの純白の声が自分を呼んでいる、とナパクスコには思われた。
ナパクスコは生れ故郷のチチカカを去り北を目指しアンデス
の山を下って行った。平地の森林地帯にさしかかったころ、一羽のコンゴウインコに出会った。その鳥は付かず離れ
ず後になり先になりナパクスコ共に進んだ。ナパクスコはその鳥をララと名づけた。
彼らはジャングル地帯へと入って行った。ナタで道を切り 開 き進んで行った。北の方角へとナパクスコを導きなが
らララの動きは活発化した。
彼の前方を飛翔しながら突然ララが鋭い鳴き声をあげた。一頭のジャガーがナパクスコを待ち伏せし隙を狙っていた。
夥しい数のコンゴウインコがナパクスコとジャガーの間の中空を飛び交いジャガーに向って鋭く威嚇の
叫び声をあびせた。一羽の巨大なコンゴウインコが音も なく背後から滑空しジャガーの腰骨の間の急所をその鋭い
嘴で突き刺した。ジャガーは後ろ足を引きずりながら逃げ 去った。 ?
jジャングルを切り抜けると肥沃な草原であった。ララはナパ クスコの肩にとまり頬づけをしながらプラチナの純白の
地は近いと言葉ではない声で言った。ナパクスコはうなづいた。
(4)
食人種ミード族は密かにコパンの地を包囲し、町は重苦 しい大気に覆われていた。ミード軍の隊長グロッソは
一斉攻撃の右手を高々と挙げた。その瞬間太陽から目には見えない無数の黄金の矢がミードの軍隊の目と
耳と喉に突き刺さり、全軍は倒れ芋虫となった。鳥々が飛来し芋虫を啄ばんだ。町は再び明るいプラチナの光
に満ちた。住人は起ったことについては誰も何も気付 かなかった。パコとララだけがことの事実について知るのみであった。
ナパクスコはララを肩に町中へと歩み入った。道行く人々
はナパクスコとララを包む柔らかな黄金色のオーラを見た。一人の男が神の使いが来たと言った。噂は広がっ
た。ここから見えるあの谷間がプラチナの純白の光の 源だとララがナパクスコに言った。ナパクスコとララは
その谷の森の中へと入って行った。
ナパクスコは潅木に囲まれた池で沐浴をしている女を見 た。女はプラチナの純白のオーラに包まれていた。マ
マルーナであった。ナパクスはこの世のものとは思えない美しさの前にひざまづいた。、パコとララは互いに頬
を交しあった。ナパクスコはチチカカから持ってきた黄 金のネックレスをママルーナに捧げた。ママルーナは
ナパクスコの求婚を受けいれた。パコはママルーナの ペンダントの一部を切りとった。それはママルーナの
偉大な祖先の聖なる遺骨であった。ララはそれをナパ クスコの胸の肉のなかに埋めた。
人々は宮殿の中央広場に集まった。ママルーナとナパクス コが人々の前に現れたとき、二人はプラチナの
純白と黄金の光のなかに煌いていた。煌きは広がり
広場全体を包んだ。厳粛な光のもやのなかで訪れた人々はコカの葉を噛みチチャ酒を飲みながらママルーナ
とナパクスコの美しさに酔った。
(5)
星々でいっぱいの夜、ママルーナはナパクスコを彼女だけが知る洞窟へと導いた。場所は二人が初めて出会った池の上方にあった。洞窟は鈍い厳粛な光にみちていた。中央には泉が湧いていた。洞窟の天井は天蓋であった。泉のほとりで二人は隣りあわせて上向きに寝ころびその天蓋を見上げていた。
北斗七星のある同じ場所にナパクスコは南十字星を見ていた。彼女はすぐに彼はチチカカの夜空の下にいることに気付いた。天蓋はコインの裏と表のように二重であることを二人は理解した。二人にとって、距離には何の意味もなかった。
I
同じ夜、ヤシュクックは星々の動きを観測していた。彼は天の川のなかにいまだ知られていない寄り添うように光る二つの星を見た。一つは金色に光り、一つはプラチナの純白であった。彼は手燭の光をたよりにこの事実を記念碑の石に刻み込み記録した。彼はかってママルーナが彼に言った天体についての異論を思い出していた。
I
夜半、ヤシュクックは家に戻るとマルガリータにこのことを話した。彼女は微笑んだが何も言わなかった。彼女は既にすべてを知っていた。二人は寝室へと赴き深い眠りに落ちて行った。
夜が明けるとコパンの町とその周辺から人はかき消えていた。何が起りそしてまた人々は何処に消えて行ったのか、知る人は今もいない。

ゼウスとヘーラー
この宇宙にカオスが出現する前、世界は乳白色の霧に覆われていた。霧は無限の空間に充満していた。
霧は神々、宇宙、森羅万象そしてまた目には見えない人間の抽象概念をも含み、すべてを内包していた。同時にそれらすべてはそれら自身の形態が全く異なっていたとしてもなお、乳白色の霧自体と同一であった。
乳白色の霧は万物の根元であった。
女神たちの間でのゼウスの評判は良いものではなかった、なぜなら女神たちはゼウスに対して肉欲を感じながらも互いに牽制しあっていたからであった。そんななかで、ヘーラーはゼウスの噂を耳にするたび、眉をひそめるだけで、なにも言わなかった。
ゼウスがヘーラーに近づき手篭めにしようとしたとき、彼女はゼウスの腕の中で身体をねじると、その肘でゼウスのみぞおちをしたたかに突いた。
ゼウスはうずくまった。
ヘーラーは静かにゼウスに言った。
「私を欲しいのであれば、まず最初に貴方はテニスと離婚し子供たちとも別れなければなりません。」
ゼウスはヘーラーの目のなかに無限の母性を見た。その目を見ながらゼウスは言った。
「私は貴女に従うことを誓う」
ヘーラーは厳粛に言った。
「如何なる他の女性とも交わってはなりません。」
ゼウスは言った。
「なんということを、私は貴女だけのもの。なぜにこの私が不実であることができましょうか。それよりも、豪華盛大な結婚式を挙げましょう。」
婚約は成立した。ヘーラーはゼウスの力強い腕のなかに倒れこんだ。
樫の木々の梢は天蓋を掃き清め、黄金色の雨は大気と大地を澄みわたらせ、森羅万象は生き生きと輝いた。大鷲は天空の遙か高く整然と静かにその編隊を展開し警戒の任に当った。
オリンポスの宮殿は正装した男神と、豪勢に競い着飾った女神たちによってあふれた。ライヤの琴の響きと共に小鳥たちはコーラスを歌い、ニンフたちは中空に踊った。
ゼウスとヘーラーがその姿を現す。宮殿はヘーラーの無垢の純白に驚嘆しどよめき、全宇宙はヘーラーの深い輝きに満ちた。女神の中の女神の登場であった。ギリシャの全土でこの婚礼は三百年の間続いた。
結婚して後、ヘーラーは将来の何時の日にかゼウスの決定的な敗北という漠然として重苦しい不安を感じていた。その上、折につけ彼女はゼウスの頻繁な浮気の噂を耳にしていた。ヘーラーはそんな重苦しい胸の内をガイアに打ち明けた。ガイアはヘーラーを慰めたが、これといった具体的な解決策を提示することはできなかった。ガイアは何も言わずに一つのザクロの実をヘーラーに与えた。
宮殿に戻るとヘーラーは、イリスとホーラーに極秘裏、ゼウスの後を付け、目撃した事実について報告するよう命じた。もたらされた数々の報告はヘーラーの嫉妬心と憤りをメラメラと燃え上がらせた。。
ヘーラーはゼウスを宮殿の大広間に呼び寄せゼウスの不実を咎めた。ゼウスは言を左右して彼女の詰問ををはぐらかせた。遂に彼女はセレーネ、ハリスト、ラミア、イーオーなど浮気相手の名前をあげ、逐一彼女たちと如何に淫らでおぞましい行為に及んでいたかについてゼウスを糾弾した。
もはや抗弁もなく、カッとなって我を忘れゼウスはヘーラーの髪を鷲づかみにすると彼女を大広間の天井に吊るした。ヘーラーは簡単にフックを外して下に飛び降り床の上に立った。その瞬間、ゼウスは猛烈な頭痛に襲われた。猛烈な頭痛は百年という長い間続いた。
ある日、ゼウスはヘファイトスに命じ自分の頭蓋骨をマサカリで割らせ、その中を調べさせた。中からは槍と盾とで武装したアテーナが現れた。
ヘーラーはアテーナを自室に呼び寄せた。アテーナはヘーラーの前に片膝をつき右手を左胸の上において座った。ヘーラーはアテーナにアテネ
ポリスの統治を命じ、またその手にかってガイアから与えられたザクロの実を渡した。アテーナはザクロの実をアテネの丘の聖なる洞窟の奥深くに安置し、その洞窟の出入り口を厳重に閉じた。
一方、ゼウスは腹心の側近に、ゼウスとヘーラーとは離婚の危機にありゼウスは近々絶世の美女と結婚するであろう、との噂を流布させた。噂は広まった。噂は更に膨らみ、その美女が真紅のドレスを身にまとい宮殿のすぐ前の道を通ると言う。これを聞いたヘーラーは怒りに眉をつりあげ宮殿を飛び出した。ヘーラーは金切り声を発しその美女に飛びかかり真紅のドレスを引き裂いた。ドレスの中から現れたのは土でできた人形であった。
ヘーラーは宮殿に戻った。宮殿にはゼウスが待っていた。二人はまた元の鞘に納まった。
チタノマキアの戦いでクロノスとタイタンの一族を滅ぼしたゼウスは天界を支配する神としての地位を獲得すると共に、新しい秩序と調和とを全宇宙に確立した。神々のなかの神の誕生であった。
然しながら、その後のゼウスに起るであろう事態をいったい誰に予想し得たであろうか。オリンポスの神々と不死の怪物であるギガースとの間には確執が存在していた。結果としてギガントマキアの戦いの勃発であった。
強力な大軍を引きつれてギガースはオリンポスの聖域に侵攻した。オリンポスの地はたちまち危機に瀕した。これに対しゼウスはヘラクレイトスを召喚し、何物をも貫く強力な弓矢を与えた。ヘラクレイトスはその剛力で弓を引き絞り矢を放った。矢はギガースの心臓を貫き、それと同時にゼウスの持つアダマスの鎌が大地を揺るがし大気を裂いて閃いた。即座にギガースの軍隊は壊滅した。戦いはオリンポスの完勝で幕を閉じた。
この戦いの結果、かってクロノスの時代以前は天と地の両方とを支配していたガイアの心のなかにしこりを残した。彼女は我慢をすることができなかった。彼女はとてつもなく巨大で強力な怪物キューポーンを立て、これにオリンポスを徹底破壊することを命じた。骨肉相食む戦いの再度の勃発であった。
キューポーンは大地を切り裂き山々を粉々に砕き天界をも轟音で揺るがしながらオリンポスに迫った。神々は恐怖しギリシャからエジプトへと逃れた。踏みとどまったのはゼウスとヘーラーとアテーナだけであった。
ゼウスとキューポーンの一騎打ちはキューポーンの勝利に終り、ゼウスは一敗地にまみれた。ゼウスは八つ裂きにされコーピリオンの洞窟に閉じ込められた。一方、キューポーンもまた重傷を負い治療のためガイアの元に戻った。
ヘーラーはアテーナとその軍団にゼウスの救出を命じ、ゼウスをヘーラー生誕の地、サモスへと運ばせた。ヘーラーは聖なる泉から流れ出る水でゼウスの身体を清め治療した。 ゼウスは復活した。
重層の黒雲が厚く覆う天蓋の下、森羅万象は不吉な兆しにおののき震えていた。ガイアは極秘裏にヘーラーを自分の宮殿に呼び寄せた。ガイアの部屋は無垢の純白のバラの花々で一杯であった。侍女が緞帳のカーテンを下して辞し出入りの扉をピタリと閉じて去った。
室内は純白のバラから放出される柔かな光と芳香に満ちた。ガイアとヘーラーは互いの心の内を分ちあっていた。ガイアは非常に用心深く遠まわしな言い方で、力それのみでは決して宇宙を支配できない、と話した。ヘーラーはガイアの言うことを正しく理解した。
ゼウスとキューポーンとはその最終的な雌雄を決すべく深く高い天空で再度の対決となった。
アダマスの鎌はひらめき、雷の轟音は天を揺るがし、噴出する炎は走り渦巻き、太陽と月の軌道は支離滅裂に乱れ、天蓋には無数の亀裂が生じ、星星はあらゆる方向に散乱し、全宇宙は崩壊直前の大混乱に陥った。
「モイアー」
というガイアの声をヘーラーは聞いた。ヘーラーは直ちにアテーナを呼びよせた。即刻に重装備をしたアテーナがヘーラーの前に立った。その手にはかってヘーラーから託されたザクロの実が握られていた。アテーナこれをモイアーのもとへと運び自らモイアーの手に渡した。その実はすべての女神たちの英知と平和への願いとが込められた実であった。
実のところ、モイアーは彼女の持つ勝利の果実を与えるようキューポーンから脅迫されていたのであった。彼女はザクロの実を勝利の果実であると偽ってこれをキューポーンに与えた。キューポーンはこれを食べた。キューポーンはたちまちにその怪力を失った。
天空での死闘は一変した。最終的にゼウスはキューポーンをシチリアにまで追い詰め、エトナ火山の下にキューポーンを封印した。ゼウスは全宇宙を崩壊から救うと共に、森羅万象の究極的な秩序と調和とを確立した。世界は再びヘーラーの深い輝きに満ちた。
黄金色の光に輝きながらオリンポスはゼウスの凱旋を迎えた。すべての神々はゼウスを全知全能の神として承認した。
カナートスの聖なる泉で身を清めたヘーラーは自分自身のすべてをゼウスに与えた。ゼウスは
ヘーラーの誠実と献身そして貞節、また同じようにその英知と勇気とを深く理解した。乳白色の霧のなかで二人は深い愛のなかへと進み一つとなった。時間も距離も空間も森羅万象もすべてが一つとなり乳白色で一面のカンバスのなかに塗りこめられた。
認識されているかいないかに関わらず、大宇宙のなかで一つのものはすべてであり、すべてのものは一つであり、私たちそれぞれはすべての物質と共に各々完全に独立しながら、乳白色の霧という一つものとして今もなお存在し続けている。

大晦日から元旦へ
森羅万象は
たえず動き変化し続けている。
けれども時間そのものは
動くことも変化することもない。
それは謂わば無ないし虚とも呼ばれ得るであろう
抽象概念であると私は定義づける。
私たちは時間という尺度なかで
私たち自身の生を営んでいる。

三月十一日夕刻のある風景
ロダンの鼻の潰れた男みたいな
ゴッホの自画像の
耳に包帯を巻いた男が
こんな場末のラーメン屋で
横文字の小冊子を
読んでいる
俺はひとり
今日はじめての食事をしている
午後五時半
貧乏が当たり前の世の中にならなっくっちゃあ
終る、
そんなことをふと考え
食事を終り
外に出る
白い梅の花の
まっさかり

プロジェクト at Dawn 3・22
ジーン クレイトンは再び燃えあがって
お互い一世一代、
あとがきについての原稿の
著者の原文を凌ぐ素晴らしいプルーフが
即日の深夜に送り返され
ビリーからは
留守電に
よろこびのメッセージ
かって呉昌碩四十二歳
白文「金膨」 ・ 朱文「白寿」を
両の手に
中国のてん刻界に登場したが
俺は抱えきれないほど、
フィリス詩二篇を冒頭の序に
世界の桧舞台に打って出る
その万全が整った
一九九九年三月二十二日。

死生眼 (2)
ー
今日のこの春のお彼岸の日に
死は
不可避だから
自分は
自分自身のそれが
どのような態様になるにしろ
自然に迎え入れたい、と
願う
他人の死についても
自分は
そうであったかと
同じように静かに
迎え入れたい

朋来依遠方
「今回、俺んとこはビールと日本酒だけでね」
「ビールやワイン類のこれ以上はどうも」
「それじゃあ、持ってきてくれたヘネシーのブランディーかい?」
「ああ、VSOPにしようや
XOはあとで自分で勝手にゆっくりやってくれ
だけど、君の料理はなんでこんなに美味しいんだろう?」
「伊達の一人暮らしじゃあないよ」
「うん、もっともだ」
出発間際に細君ナンシーのパスポートの期限切れが判明
急遽、今回は仕事をかねてビリー一人での来訪。
銭湯に行き温まりくつろぎ、
上野の西洋美術館でゴヤのエッチングを見、
日・フィルでのサンサーンスのオルガン付き三番を聴き、
歌舞伎を見、
フィリッピン・カラオケ・バーで深夜まで飲み歌い踊り
発散。
「十一月にはナンシーと一緒に来なよ必ず、な」
「うん、君も十月には花嫁さんをつれて、ニュー・ヨークで。そ れにしても楽しかったなあ」
「李白が言ってるぜ、朋遠方よりきたるって」
と、
ビリーは言葉に詰まり。

光への方向
長いあいだぼくらはたがいに平行に歩いてきて
むろん誰もがそうであるように
ぼくらにもいろいろなことが
ありすぎるほどにあった
乗りこえてきたのではない
ただどこか確かな方向でなにかが光っていたから
ぼくらはそのほのかな光をとおく目あてにして歩い
てきて
そんなたがいの線がここで交差したのだろう
光はまだ依然としてどこかにある、と
たがいにわかりあえるものだから
ぼくらはその光の方向への歩みをとめない
ぼくらは歩みつづける

わが愛猫
かってミーは
家の中であればいつでもどこでも
人間みたいに大きく四肢を伸ばして腹を上向け
万歳のスタイルであきれかえるぼどに悠然と
眠っていた珍しい猫だった
それは二階の子どもたちのベッドの上であったり
居間や私の仕事場のど真ん中であったりで、
箪笥や本棚の上とかでは
そんな眠りかたを見た覚えはない
早朝に頬っぺたをなでられて
起こされるのは嫌になったものだから最近は
私の寝所とは隔絶してたがいに夜を過ごしてきているが
ドライフッドにも缶詰フッドにも慣れ親しんできた彼女が
缶詰フッドに関してはそのたんび
餌皿を洗って新しいものを盛らないと
フンといった表情になり
決して食べようとはしなくなった。
猫ってやつは
まーったく

戦 い
俺に安心はない
俺は安心を嫌い
俺は砂漠を目指す
感傷なく
砂漠は肥沃で
ギラつく太陽を受けて耐え
砂漠は拒絶することなく
砂漠は迎え入れ
無尽の宝庫となり
激しく
熱くそして寒く
ああ、
血を凍らせ沸騰させる
はかりしれない
未知。

年齢と友情
おれたちも年齢だから・・・・・、言いながら
テーブル上にアメリカ製のビタミン栄養剤のビンを置き
毎朝かならず一錠、一年間分はある
おたがいに体は大切にしようや、とロバート
うん、ありがとう
私はうなづきながら
ふっと目頭あつく
数日後、
台湾経由で来日の細君のマリルーが加わり
台湾製ウーロンの豊潤な香りと味を楽しみ
シャンペンをぬき例によってすき焼きの宴
飲み、食べ、談じ、歌い
若いエネルギーを発散させ
翌朝、
昨夜の酔いっぷりときたら
どうしようもなかったぜ、とロバート
二日酔いのなか、なんとなく年齢を思い
その場でみやげのウーロン茶と一錠のビタミン栄養剤を食し

食べる
食前にジョッキ一杯のビール
椅子の上の背筋は伸び
左手は膝の上に軽く置き
右手の箸はテーブル上の料理を口に運ぶ、
顎と舌の筋肉を躍動させ
噛み、砕き、味わい、ゴクリと喉に送る
今日のようなこんな夜には
喉を通るときの味が一番、
胃に落ち込んでさらに充足を覚え
食べる、とは
儀式であり戦いであり
また精神の開放であり
食べる、
すべてを忘れ
今の今をたのしみ
また、明日のために

渇 望
「放てば満てり」とも、
煩悩に焼かれ
焦がれ
放つに難く
また、
愛を告げるに
おそれ
猜疑の心に
踊らされ
憂愁に沈み、
時に
あらぬ想いに
踊り
至りて、
言葉を
知らず

渺々萬里
彼方ニ光ル一ツノ点。
イマ、時空ヲ超エ。
無、虚、非在、ノ在。
絵空事。
絵空事ノカナシミ。
絵空事ノムナシサ。
非在トイフ在。
在トイフ非在。
確タル、
光。
目指シテ、
ソノ光ノ方向ヘ。

大晦日・元旦
「おお、チュウさん久しぶり。きのうの午後、管制から連絡があっていきなりの今
夜だよ。今年はゆっくり出来るかと思ってたけどそうも行かないや」
「すっげえ酒くさいよ。挨拶の時は後ろにいなよ、ヤバいぜ」「ふーん、そうかい。それじゃあ俺が今日はまんなかで音頭をとる」
恒例の年末年始の神社警備、今年はお伊勢の森の鎮守さま。
大晦日は朝から飲み出していて
昨夜は誰かに電話をしていたような気がし
何をしゃべったものか気持ちもおもたく
それでまたまた酔いにもぐりこむ
人生およそイコール芸術だ、と
粋なことを書き送ってくれた
友人のことなど思い出し酔い尽きて
また一眠り、
夜に目覚め急遽バイクを飛ばす
酔いか年齢か、
久しぶりの夜警はすぐ脚にくる
遠くの寺から除夜の鐘、と
境内から
名物のお神楽太鼓・大太鼓の乱れ打ち
ドドーン ドドーン ドドドン ドン ドン 55 03
タタンタタン ドドドン ドン
ドドン ドドドン ドドドン ドン
カンカンカンカン ドドドン ドン
ドドンド ドドンド タタタンタン
タンタンタンタン カッカッカッ
ドンドンドンドン ドドドン ドーン
延々続くその音とリズムに全身をゆだねゆさぶられ
第二駐車場満杯、了解、第三駐車場五台の空き、了解
止めろ、流せ、右、左、直進、と
俺はひっきりなしの車の出入りをさばく
酔いと緊張のなかでの太鼓の音。
俺はシャッキリとして汗をかき
五十数年を生きてきて
こんなにも素晴らしい経験はいまだなかった
消えていくものは消えていく
そんな思いも頭をかすめ

詭 弁
信ずれば福がある、ということばの裏にある論理はこわい
逆も真なのであれば、信じなければ不幸になる、ということになる
目には目を歯には歯を、もありふれた恐ろしい復讐の掟だ
右の頬を打たれなば左の頬をも差し出せは、やくざ者の大親分の
心配すんな俺に任せておけ俺が倍返しをしてやる、に似ている
俺はその男に言ったもんだった。
右の頬っぺたをひっぱたかれたらな、それだけで忘れっちまいな
少々の痛いぐらいのことはどうってこたあねえ
喧嘩なんかしなさんな。
多分、お釈迦さんもそう言うと思うぜ、と。

日 記
エカテリナもアナスタシャも枯れ去って、
クイン・エリザベトの花も終った。
アフリカから九九パーセント純純粋の
金の原石が到着し記録された。
季節外れの紫色の菫だけが二輪
冬を耐えひっそりと道端に咲いている。
十一月二十一日、フィリスさん離日の送別会の日
まるで忘れていたアメリカの The National Library of Poetry から
Howard Ely, Managing Editor 署名の表彰状が届く。
キャロル ヘンリーにあげた自分の詩の
"An Afterimage" が応募のセミ・ファイナルに残り
決勝は来年の春とのメッセージ。
そのコピーをビリーとジーン クレイトンにファックスで送 り
フィリスさんが滞在中の我孫子へと赴く。
送別パーティの後
ローレル女史と明方まで話しこみ、帰宅。
二十二日、ジニン クレイトンからファックスが届いてい る。
すぐに電話をくれ、とのメッセージ。
電話をする。翻訳技術についての長話。
「気をつけなきゃあ」
「「うん、わかった、ありがとう」。
フィリスさんには龍安寺の石庭のイメージにつき
彼女の 文体に真似て電子メールでメッセージを送った。
フィリスさんの詩 「大理石 (Marble)」 の翻訳にとりかか る。
たぶん中国名だろう、Kwan Yinの名前についてさっぱ りわからない。
問い合わせの簡単な電子メールをフィリスさんとCCでビリーに送る。
折り返しビリーからファックスで「観音」の堂々とした二文字の見事な手。
晩食は一番で酒四合とつきだしだけ。
昼飯も酒五合と肉野菜炒めだけ。
ここのところめっきり食べ物が喉を通らない。
わが愛猫ミーワーズ、俺のベッドのど真ん中。
今晩の俺は二階のベッド。
ぜんぜんさみしくはない、楽しい。
だけど、からっきしモテはしない。
その後
(一)
本国のアルバケルケ市に戻り
旅の疲れからやっと回復した
フィリスさんから連絡があり
龍安寺の
石庭についての詩が
できそうだ、と
伝えてきた
自分にはとってもできないけど
彼女にならできる。
そう考えると
うれしかった
(二) 1
サヨっぺも
ヒロっぺも、
みんな辟易して
俺から逃げて行って
しもた。
奈良の
大仏さんも
薬師さんも
あきれかえって
笑ってらしたが
俺の女漁りは
まだ続く。
おっ、チンポコがまた
おっ立っている
困った
こっちゃ。

ドライブ
ハリントン・パークから
ハドソン河沿いに
ウエスト・ポイントの上流をめざし
ピーター・ポール・アンド・マリーの歌声に乗って
車は走るひた走る
スピード時速七十マイル
全面したたる緑の
巨大な丘を上り丘を下り
平地を突っ切って
山裾を迂回しまた丘を上り
突如、
群青と白と青と緑が
水平方向巨大にうねり重畳の
大パノラマが展開し
大きくゆるやかに右に左に道はカーブし
走る走る車は走るひた走る
谷底めざし
駆け下り
また突然に
赤茶色の大絶壁が
ガガーン
眼前に迫る
ここでの自然は広々大
たおやかな表層の下
獰猛な獣の力を押し沈め
恐ろしく
巨大だ
ハドソン河を右にして
ピーター・ポール・アンド・マリーの歌声に乗り
一路ウエスト・ポイントを目指しながら
車は走るひた走る
丘を上り
さらにまた
丘を上り

早朝の風景
六月十二日午後ニュー・ヨークのラ・ガーデア空
港着ビリーの出迎えを受け彼の新居(昨年八月移転)
へ以前本誌で紹介した豪壮なゲスト・ハウスは今はビリーが所有し居住するところとなっていて翌、早朝の起き抜けにその豪華な邸宅の寝室の
窓から目に染みる芝生の光に気分刷新、ひとり散歩に でかける
朝露を踏み
ハリントン・パークの湖の
原生林の小径を行く
入口広場の
ドッグ・ウッドの密生は
豪勢な女盛りの純白を放射し
黒紫の楓の木々
いまだおさない桜の木
巨大な樫の木
アメリカ杉
欅の木
薄暗い光の中に
数百年の風雪の
樹肌に全面薄苔をまとい
あるいは蔦をまとい
靄の中に立ち続け
湖面の彼方は
霧に煙り
大気は茫洋として
なべてを包み
リスが野兎が地面を走り
子連れの鴨が
列をつくって湖辺を歩く
径端の小石を拾いポケットに入れ
また
カナデアン・グースの
落ちた羽根を拾う
[付記]
十二日の夜はビリーの海の仲間の四十五人も
の来訪のホーム・パーテイがそこで行われたが、五十 人をも飲み込んで邸宅はまだまだ余裕十分。私は流石
に疲れ途中でダウン、席を外し寝室で横になりしばらく 休憩をとった。ビリーはこの邸をとりまく巨大な森を自分
で名づけて「ロビン・フッドの森」だ、と言っていた。

花はなぜ美しい
直也くん美華子さん
この春先にきみたちの婚約の話を聞いたとき
なぜかふっと
二つの大輪の花のイメージが
くっきりと私の脳裏をよぎりました
それと同時に
「花はなぜに美しいのだろう」という
きわめてストレートで素朴な思いが
私の中にわきました
この六月の中旬に
ニュー・ヨークからマイアミそしてシカゴを回るアメリ
カ合衆国への
二週間の旅のさなかにも折につけ
「なぜに花は美しいのだろう?」というその素朴な思
いは
私の胸の内をたえず去来し
それはまるで答のない漠たる思いであったことも
また確かなことでした
私は七月の二日にまたシカゴに向けて成田を発た
なければなりません
四日のきみたちの結婚式の日はアメリカでは独立
記念日で
その日、私は友人のパーテーに出席しているはず
で
その出発前のあわただしい中でこの詩をまとめてい
ます
花はなぜ美しいのでしょう
本当に花はなぜに美しいのでしょう
考えてもみればそれに対する答はありそうですが
水をいくら分析し説明してみても
水そのものをわかることは不可能であるように
おそらくそれは永遠に答のない疑問であるかもしれ
ません
きみたちの婚約の話を聞いてからずっと
そんな思いが折につけ私の胸のうちを去来してい
ます
「花はなぜにうつくしいのだろう」
私はそうした疑問をあたえてくださったきみたちに
深い感謝の念をいだきます
そしてそれはまた同時に
きみたちに対する祝福のことばとなってくれるもの
だと考えます
直也くん美華子さんありがとう
ほんとうにあめでとう

端午の節句の日に
友人がさしいいいれてくれた
一束の菖蒲を空の湯船に入れ
自動スイッチを押して風呂そたてる
首まで湯に」つかる
香りほ無意識の意識に働いているのだろう
不思議にゆっくりとくつろぐ
何なんだろうな
まるで意識されない
サッパリとしたこの感覚は

美しい精神
寺島靖夫画集 「竹馬に乗って」 に寄せる
高く澄んで明るい
日本アルプスの
大空の下で育まれた
あたたかい精神が
竹馬に乗って
やってぉてきてくれた
なんという
邪気のなく美しい
こころねだろう
うれしい
ほんとうに
うれしいい

カクテル ハポネッサ
二十五度の格安寶焼酎を
静岡産の高級抹茶で割って飲む
うまくもないまずくもない
何の意味もない、プファーッ

私たちの基底にあるもの
詩は如何なる社会思想をも包含しまた宗教思想をも内包し得るのです。然しながらそうした諸思想に追随するものでも或いは喧伝するものでもありません。
詩が人々を感動させ得る理由は詩そのものの中で感性と知性ないし精神性といったものが渾然として結合しあっていて論理性自体とも密接にからみあっているからであろうと私は考えます。
私たち Poetry Plaza
が追い求めているものは芸術の領域であってメンバーの間でもそれぞれ異なった様々な思想あるいは見解がこのサイトに提示されており読者にとって何かしら心の糧となり得るる価値のあるものであることを望みながら私たちの作品はそのまま一つの客体として読者の前に投げ出されています。

七十五歳
視力は極度に落ちて悪く半めくら
どんなレンズも効かず悪くなる一方
青春時代左肩脱臼
両足首は複雑捻挫で重たく痛く
腰椎三本金属固定
右膝人工関節にて代替
サイボーグはまだ此処で元気で
未来に向って激しく燃え立っている

私が詩作るとき
私が考え詩作するとき
主観と客観とが絶えず私の意識のなかで
せめぎあっているように思われます
このことはおそらく
普遍とは何処にあるのかという
避けることのできない問題意識が
絶えず私につきまとっているからなのだろうと
私には思われます

マドンナ フォーエバー `
落葉した薄暗い藪のなか
並外れた白が黙して静かに
直立している
(註)
マドンナ フォーエバーとは雪柳のことで作者の造語です

日記抜粋
ガラスの引き戸からの太陽光
暖かく明るく静か
サイドボードの片隅
一輪挿しのなかの
雪柳の無垢の純白一枝
私の前
玄い茶碗
茶器、茶匙、茶筅
訪う人
なし

事 故
ある動物園で若い女性飼育員がライオンの檻を清掃中に雌ライオンに襲われ重傷を負ったというニュースをラジオは伝えた。重傷の飼育員は救急車で病院に運ばれたが病院に着いたときにはその女性は死んではいなかったと報じられた。
翌日さらにラジオはその負傷した飼育員の生死には触れずに当面の間この動物園は休館する旨を伝えたがそれ以降このニュースはラジオから消えた。
このニュースは私のなかには一抹の疑問を残して消えて行った。

共 生
十二階にある
コンクリートで閉ざされた住いで
互いに仲良く
愛猫のボビーと共に私は生活をしている
I
私も孤独だがボビーもまたそうだろう
けれども孤独を共有しながら
私たちは幸せであっても不幸ではない
特別に為すこともなく
日々は過ぎて行く

乳白色の靄のなかで
俺は一体に何者であるか
俺に主義主張はあるか
その答は横に置き
俺は考えることをやめる
俺は何者たらんとも
欲しはしない

狂人に刃物
真っ昼間
人だかりの真ん中で
わけの判らないことを叫びながら
酔っ払ったならず者が蛮刀を
めちゃくちゃに振り回している

夕暮れどき
青春の十年間私は
文学にはまるで関係のない
トップアスリートであった
いま
身体は
ガタガタのボロボロ
それでもなお
最後のゴール目指して
フルスピードで走っている

無 題
生命をあたえられ
生きてきて
此処に私は生きている
精神は
さらに
燃え続けて

訓 戒
おべっかすな。服従すな。
常に庶民と共にあれ。
普遍とは何処にあるかを見つめながら
自分自身の力でまっすぐに行け。

芸術魂
林心耳先生を偲んで
「旅をするには一人がいいんだ
旅は一人にかぎる」
ぽつり一言。

ここ十数年
別離、再会、手術、惜別、新しい出会い、
予期もせぬできごと、商店街の大幅な変化、
新築された数々のビル、大震災、大津波、
数しれない大きな変化。
四歳になる愛猫ボビーとの二人暮しの
七十四歳。

眺 望
わーっ
乳白色一面の俺の視界の真ん中に新しいノッポビル
輪郭は空の色にぼんやりと溶けこんでいて
美しい
こんな風にして十二階のこのベランダに立つのは
あれから数えて年々になるだろう?

事実陳述書
毎晩眠りにつく前
翌朝目が覚めたときに突然
失明しているかもしれないと思う。
何年も前に医師は治療の方法がない旨断言し
視覚は何年もつのか知らされてもいない
従ってこのページをどれだけ続けられるか?
あまり考えず自然の成り行きに任せざるを得ない。

メンバーシップ
for Jessica Helen Lopez
生きるとは愛をかかえた悲しみであり
平等を訴えるにはけ口もない
避け得ない怒りとして君自身のなかにある
一つの個として生きるという君の不可避生が
君を Poetry Plaza にデビューさせた

未来に向う
七長篇叙事詩七篇目をものし
十分にやった、と俺は思っている
長篇叙事詩を作る人は余リいないから
世界史について再度学びさらに調べ
イメージを膨らませ過去の知識をも総合し
書くこと自体が俺の最高の楽しみだった
いま一面乳白色の視界のなかで
次のテーマについて俺は考えている

七十三歳
毎早朝起きぬけにマグカップ一杯のコーヒを喫し
数種のサプリメントを摂り血圧安定剤を飲み
それから煙草を数本楽しながらその日の予定を考える
些細なことでも最何事にもつけ
事柄を総合し決めることに時間を要すよういなっているなか
あれこれ反芻しながら一日の予定を立てる確認する
スケジュールをこなし午後にはひとり
夜おそくまで安酒をんで酔いあとは覚えなく
夜食、ベッドで眠っている自分自身を発見する
一日一メインは案件
i一日一食酒少々
時間は過ぎて行き
長寿高齢化社会の下
若くもなく年寄りでもなく
今年数えて七十と三歳

日記抜粋
ヘーラーの王杖に
カッコー鳥がとまっている
私はその鳥に挨拶をした
カッコーは私の肩にとんできて
私の耳に何事かを囁いた
(また忙しくなる)

ばかげた想い
ぼんやりとして
裕福ということについて考えている
そしてまた
幸せとは
あるいは満足とはについても

死 生 眼

生まれ
生き抜き
どうやって何処まで行けるかと
考えながら
此処でこうして
まだ生きている

地球温暖化
真冬にセミが
鳴いている
ゴッホについて
考えている

凶 兆
何時になくどんよりとした真夜中
何時になくあちこちに流れ星
多くの魂が消えて行っているか

無 為
時間が通り過ぎて行くなかで
俺は黙って何かがやってくるのを
待っている
考えることもなく心配ごともなく
俺は避けることのできない
将来を見つめている

秋の午後
淀んだ空気のなかボビーは俺のベッドで
長々と手足を伸ばして仰向けに眠っている
俺はドアや窓のすべてを開け放つ
自然の大気は渦を巻き部屋部屋を吹き抜けて
塵やほこりを吹き飛ばし通りすぎて行き
気分さっぱりとする

安 曇 野
高木国雄著 「犀川の見える村」 に寄せる
飛騨山脈の気高い山稜
白馬、穂高、槍ヶ岳
深い空のコバルトブルー
澄んだ大気、透明な水
巨大な飛騨の麓を流れ下る
犀川、高瀬、梓川
俺たちの精神を育んだ
極寒の冬
俺たちが育った大地
はるか遠くに過ぎ去った日々

老 齢
近々失明する不安を押し殺し何としてでもその前にと考え
第六番目の長篇叙事詩 「そのママルーナ」 を急遽書き終り
Poetry Plaza に転載しページのデザインを整えながら
自分はまだ何処まで行けるかと再び思う。
けれども振り返って戦時下と戦後のころのことを
考えても見れば
こんな状態はどうということはないまだやって行けるやって行く。
私はそう考えた。

ひとりごと
私にとって新しい試みとしての前衛は
何の意味をも持ちはしない、けれども
正統性とは何だろう
とりわけ、正常とは何だろう

ひとつの生存
盲目と遠耳に近く
のろのろと這いつくはりながら
両の手の杖に托して歩きながら
私は此処にある
仮想空間の此処にこうして私はある

現 実
俺たちは
見えない下り道に沿って
歩いている

覚書 (2015年7月2日)
帰らざるわが長旅は続く
何が幸せであって何が不幸せであるか
誰がよく言い得るか
両眼を黄斑変性末期にして視力は衰退を続け
何時の日にか消えうせようけれど
まるで邪気のない愛猫ボビーと共にあって
ひとり身の今をこそ楽しむ
「ママルーナ」をしあげるまでには
まだ時間が残されているだろう
俺になさけは無用のようだ

2018年元旦
ぼやけた風景のなか
終りのない旅が
さらに続く

大晦日
独特な雰囲気をおびた
あわただしく熱っぽい
クリスマス前後の一週間
人々の気分は依然としてせわしなく
けれども時間は大晦日へと静かに
途切れることなく進んで行き
魂を静める
除夜の鐘の音
おちこち

認 識
論理がその基盤とするものは感情であって
論理は感情を正当化するための
謂わば一つのツールであるに過ぎない
今、たそがれの時刻のなかにあって
幸か不幸か俺は未だ
幽霊を識(み)るまでに至ってはいない
人々は口を閉じ
とぼとぼと歩いている

BACK TO HOME